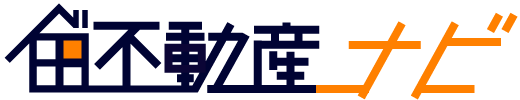不動産売却の流れ
保有する不動産を売却する場合は、基本的に不動産会社を介して売買を行うのが一般的です。不動産売却といっても不動産の査定から媒介契約、売却活動、売買契約、引渡しに関わる各書類の作成および手続き申請といった多くの工程があります。
家を売却する流れ
所有している家を売却する際の流れを分かりやすくまとめています。
保有する不動産を売却する場合は、基本的に不動産会社を介して売買を行うのが一般的です。不動産売却といっても不動産の査定から媒介契約、売却活動、売買契約、引渡しに関わる各書類の作成および手続き申請といった多くの工程があります。他にも売却して終わりではなく、売却したことで売却益がでる場合には確定申告の手続きもしなければいけません。
そういったことをスムーズに行うために不動産会社へ依頼しますが、全て不動産会社任せではなく、ある程度の知識を持ち合わせた方が交渉時にも有利に働くこともありますので、こちらでは不動産を売却する流れをしっかり把握するようにしましょう。
実際の不動産売買の流れとして以下のような形になることが多いです。
-
- 不動産を売却する動機と目的を明確にする
- 売却する不動産の相場を調査して希望売却価格を算出する
- 売却を依頼する不動産会社を探す
- 売却する不動産の物件価格の査定を依頼する
- 不動産会社に仲介依頼をし、媒介契約を結ぶ
- 不動産を不動産会社のネットワークで売りに出す
- 購入希望者が現れたら、不動産会社を交えて交渉をする
- 購入希望者に不動産の物件情報を開示する
- 双方が合意したら売買契約を結ぶ
- 引渡し手続きを行い、不動産を引き渡す
不動産を売却する動機と目的を明確にする
不動産を売却する場合は、ライフスタイルや環境の変化で新しい住宅を購入するためであったり、別のマンションに引っ越すためであったり、親から相続した不動産を処分するためであったりと色々な目的があります。そこには、新しい家族ができたからもっと広い家に住みたいたとか、仕事の転勤で引っ越さないといけなくなったとか、親が亡くなって相続したけど遠方のため管理できないとか、土地や家を売却する時には動機というものがあります。
不動産売却ではそういった動機や目的によって、売却する時期や売却する希望価格、不動産会社が提案する売却方法、売却活動の方法など提案内容が変わる場合もあります。
例えば、お金の用立てが必要になったので所有する家を早急に売却したい場合は、ある程度相場よりお買い得な価格設定をすることで購入希望者を多くかつ早くみつけることができます。他にも複数の購入希望者がでるような立地のいい土地や建物を売却する場合は、適正な相場価格より少し金額を上げて売却することもできます。このように売主の事情や不動産の環境が違うだけでも販売価格や不動産売却までの時間も大きく変わってきます。
不動産を売却する動機と目的を明確にすることは、そういった事情や条件を客観的に数値化することができますので、不動産会社へ売買の相談をされる前にどういった動機で売却するのか、どういう目的で売却するのかを箇条書きにでもまとめて、客観的な判断材料として持っておきましょう。
売却する不動産の相場を調査して希望売却価格を算出する
土地や戸建てあるいはマンションといった不動産を売却する場合は、現在どれぐらいの価値があるのかを見極めるために相場を知る必要があります。もちろん、不動産の相場については、プロである不動産会社へ依頼することもできますが、自身である程度、不動産売却の知識や相場を知ることは、不動産会社や購入希望者とスムーズに交渉ができますので、時間に余裕のある方は一度売却する物件がいくらになるのか相場をチェックして希望売却価格を算出してみましょう。これは、不動産の周辺相場を知ることで通常売買される適正価格を把握することができ、売却がスムーズにいく希望売却価格を計算できるメリットもあります。
相場の調査方法としては、不動産情報サイトを利用して、同じ地域で構造や階層、築年数、間取りといった、似ている物件を探して販売価格を把握したり、地域の住宅情報誌やチラシでも相場を調べることができます。
ただし、調査する時間がなかったり、地域によってはあまり情報が収集できない場合もあります。そういった場合は、複数の不動産会社に簡易査定という形で手っ取り早く相場を知ることもできますので、一括査定サービスなどを利用するのも1つの方法ではあります。
売却を依頼する不動産会社を探す
不動産を売却する動機や目的、相場を把握したら実際に売却を相談する不動産会社を探します。不動産売却の流れとして色々な手続きが必要と説明しましたが、不動産会社はただ売却の仲介をするだけではなく、売却に当たっての経費がどれぐらいかかるのか、法律に抵触しているものはないか、売却によって発生する税金がどれぐらいかかるのかなど専門的なサポートもしてくれます。
ただ、中には仲介だけを淡々とこなすだけの不動産会社があったり、細かくヒヤリングを行い最大限の提案やサポートをしてくれる業者もいらっしゃいます。このように不動産会社の姿勢や対応によって売却金額が大きく左右されることも珍しくなりません。トラブルや損をしないためにも信頼できる不動産会社を見つけることがとても重要となります。したがって、不動産会社についても情報を収集し、複数の中から信頼できる経験豊富な不動産会社を選びましょう。
不動産会社へ売却の相談をする
信頼できそうな不動産会社が見つかったら連絡をして、不動産売買についての相談をしましょう。不動産売買についての相談を大きく分けると2通りのパターンがあります。1つは、現在所有している土地・建物を売却して新しい家を購入する住み替えるパターンです。こちらは、「住宅ローンが残っているけど、売却できるのか」「新旧の住宅ローンを2重で払う必要があるのか」「家を売ってから新しい家を買うのが先か、それとも新しい家を購入してから所有している家を売ったほうがいいのか」など2つの家についての相談が多いです。
相談の回答については、売却の動機や目的、条件によって変わってきますので、現状をしっかり担当者へ把握してもらえるよう努力しましょう。
買い替え時のよくある質問内容
-
-
-
- 住宅ローンが残っているけれども大丈夫か?
- 売却が先か?それとも購入が先か?
- 売却後の手取り金額はいくらぐらいになるのか?
-
-
もう1つのパターンは親からの相続など、資産として保有している不動産を売却したい場合です。特に親が他界した際に相続した実家を管理できずに無駄に固定資産税を払うぐらいなら手放したいと考えて相談される方が近年多くなってきています。
資産売却時のよくある質問内容
-
-
-
-
-
- 親から相続した遠隔地にある物件でも大丈夫か?
-
-
-
-
相談するパターンは異なっても売却する点では共通しています。売却する場合は、不動産の状態や周辺環境、敷地境界の確認、権利関係の確認、ローン借り入れの状況など様々な観点から確認していきますので、相談される際は知っている情報を包み隠さず担当者へ伝えるようにしましょう。売買後にトラブルで知っていたのに伝えていなかった場合は、瑕疵担保責任を問われる場合もありますので、ご注意ください。
売却物件の確認調査と価格査定を依頼する
不動産会社へ売却する動機と目的を担当者へ伝えて、担当者が内容をしっかり把握できたら実際に売却する不動産の確認調査と価格査定を依頼します。
価格査定は、不動産会社の売却の最初の仕事と言えますが、不動産の物件価格については、不動産鑑定士などプロが適正価格を算出したとしても、会社によっては金額が若干異なる場合もあります。
まったく同じ条件の物件は存在しませんので、ある程度の差が出てきてしまうのは仕方ありませんが、もう1つは査定方法にも大きく影響します。
査定方法には、大きく分けると近隣で売り出されている類似物件や売買成約物件のデータから簡易的に査定する簡易査定と実際に現地に訪問して現地調査を行い、正確な査定額を算出する訪問査定の2種類があります。
より正確性が強いのは訪問査定になりますが、概算的に算出する場合は簡易査定が用いられることも多いです。
簡易査定は比較的早く概算の相場を知ることができますが、実際の査定金額と大きなバラツキがでることもあります。
逆に、訪問査定の確認調査では、土地や建物の状況から近隣環境、建築法規関係、登記等の権利関係の洗い出しの他にも、周辺地域で実際に売り出されている類似物件や制約事例などの市場調査を基にあらゆる観点から総合的に適正な不動産査定を行うため、正確な見積価格を算出することができます。
簡易査定・訪問査定でも不動産会社によって細かな査定方法が異なるため、金額にバラツキがでてしまいますが、正しい価格を把握するには複数の不動産会社へ一括見積依頼をかえるといった方法もあります。
複数社にお願いして明らかに金額が低い不動産会社は除外したりとなるべく高く売れるよう話を進めることもできますし、査定価格の算出を無料サービスで行っている不動産会社も多いので、そういった方には一括見積依頼はお勧めです。
不動産会社に正式に仲介依頼を行い、媒介契約を結ぶ
不動産会社に算出してもらった価格査定を参考に希望売却価格を設定し実際に売却の意思が固まったら、正式に不動産会社へ売買の仲介を依頼します。その際に不動産会社との間で契約を結びますが、その契約を「媒介契約」と呼びます。
不動産会社が売却する物件の成約に向けての宣伝活動や調査を積極的に行わなければ、早期売却することが難しいため、売主を保護するためにも宅地建物取引業法で、活動義務や仲介手数料を明示した媒介契約を書面にて結ぶことが義務付けられています。
媒介契約書には、売却する物件の住所や売却価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、成約した場合の仲介手数料、などを明記しており、媒介契約書を交わすことで正式に売却依頼が成立します。
また、媒介契約には、不動産会社が売却活動などどういった業務を行っていくのか、売却が完了した際の仲介手数料はどれぐらいかなど契約で内容を明確にすることで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐ役割もあります。媒介契約が締結すると不動産業者は「宅地建物取引業法第34条の2」の媒介契約に則って法的に義務付けられます。
(媒介契約)
第34条の2
- 1.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
- 一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
- 二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
- 三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
- 四 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
- 五 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
- 六 報酬に関する事項
- 七 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
- 2.宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
- 3.依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
- 4.前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
- 5.宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
- 6.前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
- 7.前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
- 8.専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
- 9.第三項から第六項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。
媒介契約書には媒介契約の種別を明記する必要がありますが、主に以下の3つの媒介契約方法があります。どの契約で締結するかによって不動産会社の義務事項が変わってきますが、売却する動機や目的から希望する売却方法などを踏まえて、どの媒介契約を結ぶかを考えましょう。
-
-
-
-
-
-
-
- 専属専任媒介契約
- 専任媒介契約
- 一般媒介契約
-
-
-
-
-
-
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 【依頼人(売主)の義務】 | |||
| 複数の仲介業者へ依頼 | 出来ない | 出来ない | 出来る |
| 依頼者自ら発見した相手との取引 | 認められない | 認められる | 認められる |
| 【不動産会社の義務】 | |||
| 不動産流通機構「レインズ」への登録義務 | 5営業日以内 | 7営業日以内 | なし(任意で登録可) |
| レインズへの登録証明書の交付 | 依頼主へ交付しなければならない | 依頼主へ交付しなければならない | |
| 活動状況の書面による報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |
| 契約有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
| 成約によるレインズへの通知義務(成約登録) | あり | あり | なし |
専属専任媒介契約
「専属専任媒介契約」の場合、売却依頼ができるのは1社のみとなります。また、依頼者(売主)が自ら購入者を発見して取引を行う自己発見取引を行うことはできません。
依頼者(売主)が発見した場合でも契約を結んでいる宅建業者に紹介を依頼して仲介手数料を支払う必要があります。
厳しい制約があるのは依頼者(売主)だけでなく、不動産業者にもいくつかの義務が発生します。
契約を結んだ不動産業者は、全国の不動産情報が掲載されている指定流通機構への登録を5営業日以内に行う必要があります。
また、売却に関する活動状況を書面にて1週間に1回以上報告する義務もあります。
指定流通機構は宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣が指定した不動産流通機構で、不動産情報を共有したネットワークシステムです。通称「レインズ」と呼ばれており、4つの法人「西日本不動産流通機構(西日本レインズ)」「東日本不動産流通機構(東日本レインズ)」「中部圏不動産流通機構(中部レインズ)」「近畿圏不動産流通機構(近畿レインズ)」が運営しています。不動産流通機構を通して、年間10万件以上の売買が成立しています。
尚、4つの指定流通機構の管轄区域は以下のようになります。
| 指定流通機構 | 管轄区域 |
|---|---|
| 東日本不動産流通機構 | 北海道 東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島) 首都圏1都3県(東京・埼玉・千葉・神奈川) 北関東3県(茨城・栃木・群馬) 甲信越3県(山梨・長野・新潟) |
| 中部圏不動産流通機構 | 中部7県(富山・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重) |
| 近畿圏不動産流通機構 | 近畿2府4県(京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山) |
| 西日本不動産流通機構 | 中国5県(鳥取・島根・岡山・広島・山口) 四国4県(徳島・香川・愛媛・高知) 九州8県(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄) |
不動産流通機構「レインズ」では、依頼者(売主)の不動産情報を公開することで不動産を購入したい方(買主)に対して別の宅建業者が売却する物件を検索できるようになっており、不動産流通の円滑化を促進する役割を担っています。
つまり1社に依頼すれば、不動産流通機構「レインズ」の加盟会員業者が仲介活動に参加することができ、早期に売主と買主を見つけて不動産の売買契約を締結させるといったメリットがあります。
尚、不動産流通機構「レインズ」に物件を登録した際に不動産会社は、依頼者(売主)に対して指定流通機構が発行した登録証明書を渡す義務があります。稀に不動産流通機構「レインズ」の登録証明書を渡さない不動産会社もいますので、しっかり登録証明書をもらうようにしましょう。
不動産会社は他にも登録した売却物件が売却された際に、取引価格など成約情報を指定流機構へ通知する義務も負っています。これは、これらの成約情報を収集し更に不動産業者へ情報を提供することで、不動産流通の円滑化を図る狙いがあります。
本来であればこういった不動産の成約情報はクローズされた環境でしか閲覧できませんでしたが、昨今インタネットの急速な普及により売主が相場観を適切に把握できるように、成約価格を基にした「不動産取引情報提供サイト(RMI)」で確認することができるようにりました。
RMIは、REINS Market Information(レインズ・マーケット・インフォメーション)の略称で、4つの指定流通機構が保有する実際に売買が成立した物件価格(成約価格)などの取引情報を検索することができます。
提供される情報としては以下の項目があり、取引情報の詳細表示について方針も決められています。
| 表示項目 | 単位 | 表示方針 |
|---|---|---|
| 価格 | 百万円 | 十万円単位を四捨五入して、表示 |
| 単価 | 万円/m2 | 小数点以下を四捨五入して、表示 |
| 面積(建物・土地) | m2~m2 | 実際の面積に20m2の幅を持たせて表示。面積が200m2を超える場合は「200m2超」と表示。 |
| 築年 | 年 | 実際の築年に2年の幅を持たせて表示 |
| 成約時期 | 年月~月 | 成約された年月を3ヶ月で区切った範囲で表示 |
また、「専属専任媒介契約」では、契約の有効期限も決められており、標準的な契約有効期限は最大3ヶ月となっていますが、依頼者(売主)の申し出により契約更新することで、更に最大3ヶ月まで継続することができます。
専任媒介契約
「専任媒介契約」の場合も専属専任媒介契約と同様で売却の依頼ができるのは1社のみとなります。ただし、専任媒介契約であれば、専属専任媒介契約では禁止されていた自己発見取引を行うことができます。
ただし、自己発見取引で取引した場合、宅建業者が調査や販売活動に要した費用を請求されることもありますので、契約時にしっかり確認しましょう。
他にも指定流通機構への登録や活動状況の報告の義務はあるものの、専属専任媒介契約より制約がゆるくなっており、不動産流通機構「レインズ」への登録を7営業日以内、活動状況の報告は2週間に1回以上となっています。
ただし、契約有効期限だけは専属専任媒介契約と同様に最大3ヶ月となります。
一般媒介契約
「一般媒介契約」の場合、依頼者(売主)は複数の不動産会社へ依頼することができます。ただし、専属専任媒介契約・専任媒介契約で義務付けられていた不動産流通機構「レインズ」への登録は任意となり、1週間ないし2週間に1回以上の活動状況の報告義務もありません。
もちろん、自己発見取引も自由に行うことができ、比較的自由性のある契約となっています。
また、複数の不動産会社へ依頼する際に、他にどの業者に媒介を依頼しているのかを教える「明示型」と教える必要のない「非明示型」があります。
国土交通省の定める一般媒介契約書を利用して媒介契約を締結する場合は、「明示型」が原則となっていますが、「非明示型」を選択する場合は、特約によって非明示とする旨の条項を定める必要があります。
「明示型」の場合は、他の不動産会社(宅地建物取引業者)の名称と所在地を通知することでライバルが分かる仕組みになっています。
「非明示型」の場合は、どこに依頼しているのか何社に依頼しているのかが明らかにされませんので、不動産会社の立場としては、他社がすぐに売却成立させてしまう恐れもあるため安易に売却活動ができないといったジレンマがあります。
そういう意味では「非明示型」を選択したことで、どの会社でも積極的な売却活動が行われずに買い手が付かない状況が続く恐れもあります。
一般媒介契約の場合、双方に制約があまりないため自由な取引ができるようにも見えますが、不動産業者の立場から考えると他の業者が売却成立させた場合、成果報酬のため仲介手数料がもらえない可能性もあります。
そうなると「明示型」であっても安易に新聞折込広告や住宅情報誌の掲載、チラシ配布といった「広告宣伝費」にお金をかけにくい側面があるのが現状です。売却活動が積極的に行われなければ購入希望者(買主)も見つかりづらくなるため、不動産売却まで長い時間を要することになります。
時間がかかれば売却価格を引き下げたり、最悪の場合は買い手が付かずに断念するケースもあります。
その他にも複数の不動産会社へ依頼すると窓口が増えるため、それぞれの業者との打ち合わせ(内乱日程の調整、や売却条件の交渉など)の調整に手間がかかってしまいます。
一般媒介契約では複数の不動産会社を選べるため、うまく利用すれば業者同士で競争意識が芽生え高く売却できる可能性も秘めています。
競争意識で言えば、「非明示型」より「明示型」のほうが競争力が生まれやすいですが、一般媒介契約は比較的自由な反面デメリットもありますので、売却の動機や売却する物件の価値などを考慮してどの媒介契約を結ぶか慎重に考える必要があります。
ここまで3つの媒介契約について説明しましたが、媒介契約を結んだからといって必ず売却しなければならないといった義務を負う必要はありません。
また、不動産会社が得られる報酬料については完全成功報酬なので、媒介契約を結んだ際の委託料も発生しませんし、売却できた際の仲介手数料のみとなります。
もちろん完全成功報酬なので依頼者(売主)が売却を断念したときも仲介手数料を支払う義務もないのが特徴です。
仲介手数料
仲介手数料は、宅地建物取引業法により不動産会社が受け取ることの出来る上限が決まっています。よって、不動産会社が上限を超えて仲介手数料を請求したり受け取った場合は、法令違反となります。
仲介手数料は売買契約が成立したときに支払われる完全成功報酬ですので、売買契約が成立するまで、不動産会社へ仲介手数料を支払う必要はありません。
基本的には、売買契約成立時に依頼主(売主)に仲介手数料を請求することはできますが、売買契約成立=不動産引渡しではないので、一般的には売買契約成立時に仲介手数料の50%、不動産引渡し完了時に残りの50%を支払うのが慣例となっています。
不動産会社は売却活動の中で新聞の折り込み広告や情報誌への掲載などの広告費を出費していますが、それらを依頼主(売主)へ請求することはできません。ただし、依頼主(売主)の依頼により特別に発生した広告費や諸事情で必要になった費用などは実費にて請求することが認められています。
仲介手数料の上限については以下のように売買取引額の金額区分ごとに上限が定められています。尚、仲介手数料は消費税の課税対象ですので、別途消費税がかかります。
この金額区分ごとの報酬額は売買取引額が1000万円なら400万円を超えているから1000万円×3%=30万円ではなく、金額区分の範囲でそれぞれの率で計算されます。
例えば、1000万円であれば、200万円までが5%、200万円から400万円までの分の200万円が4%、400万円を超える分の600万円が3%で計算され、それぞれの報酬額を足したものが仲介手数料となります。
200万円×5%=10万円
200万円×4%=8万円
600万円×3%=18万円
10万円+8万円+18万円=36万円
更に消費税を上乗せしたものが仲介手数料の上限額となります。
36万円+消費税=仲介手数料の上限額
なお、400万円を超える売買取引額の場合は、「売買価格×3%+6万円+消費税」でも簡単に計算することができます。
また、仲介手数料の上限額は媒介契約の種類によって変わるということはありませんので、どの媒介契約を選んでも上限額は同じように計算されます。
どの媒介契約を選ぶかによって、1社に頼むのか、数社に頼むのかなど売却の手法そのものが変わります。非常に重要な選択となりますので慎重に検討する必要があります。
尚、媒介依頼を行う不動産会社の選び方のポイントとしては、自身の優先順位を考えた方がよいです。
気になるのは不動産会社の提示した査定価格と不動産売却希望価格との折り合いかと思います。
ただし、一番いいのでは、査定根拠の説明や担当者の対応、印象です。売却をスムーズに行うためにも不動産会社の選定は重要となりますので、価格以外にも担当者の対応なども考慮しましょう。